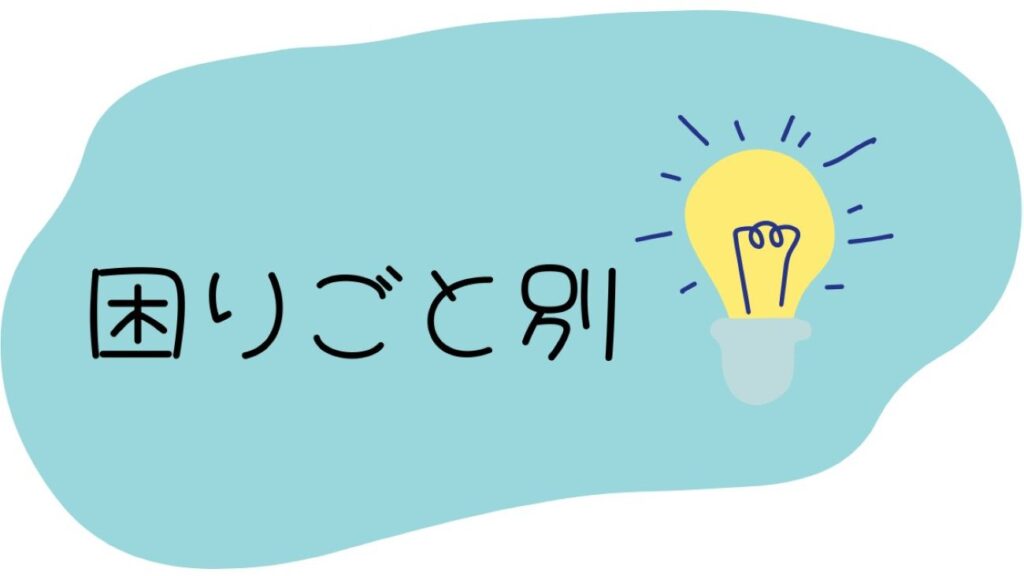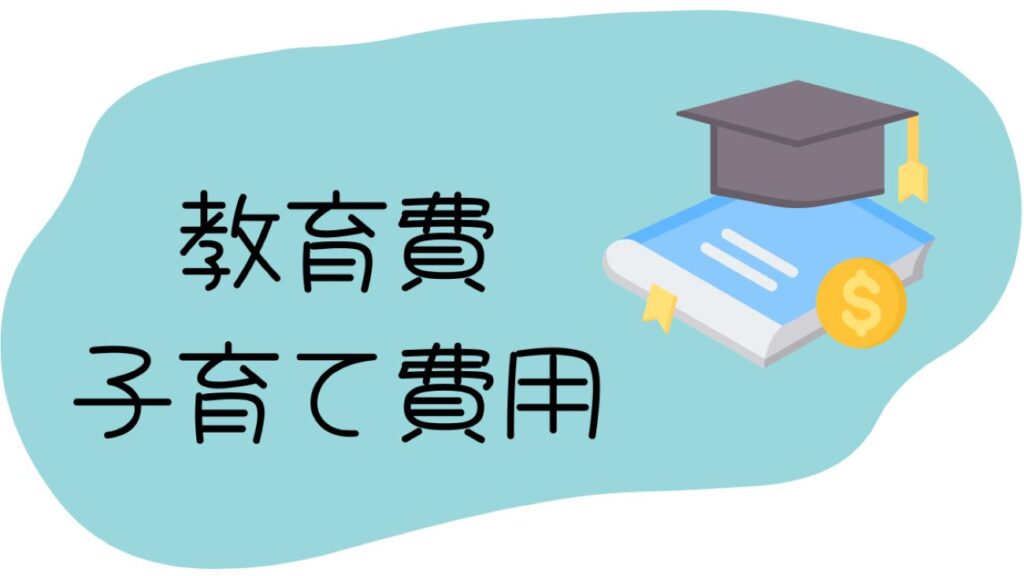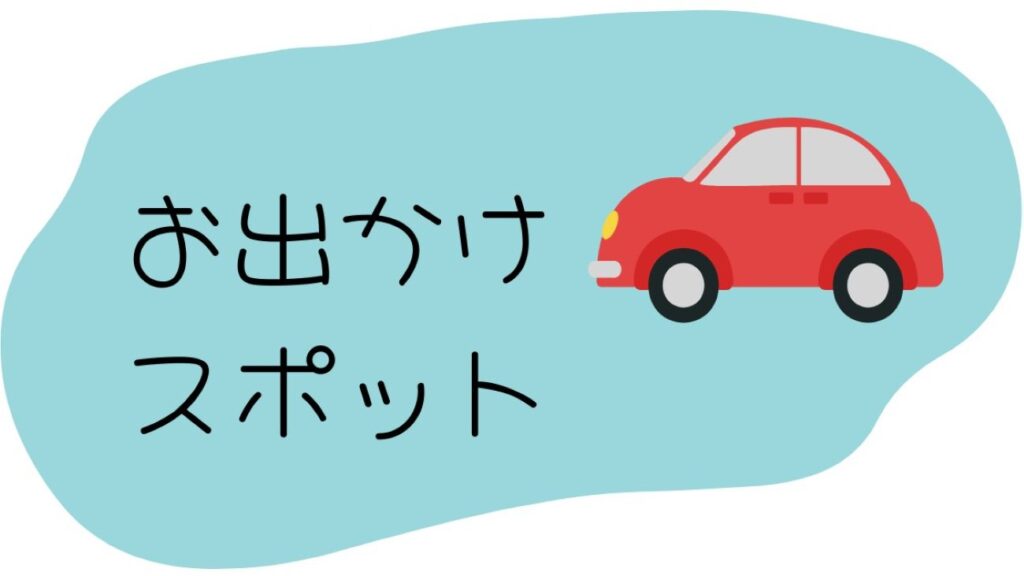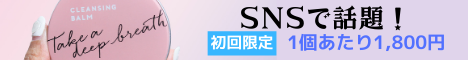兄弟喧嘩いじわるを減らすには?親ができる7つの工夫と声かけ

兄弟がいるご家庭では、喧嘩やいじわるに頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。
特に、上の子が下の子に対して意地悪をする場面を見ると、つい叱ってしまいがちです。
しかし、こうした行動には子どもなりの理由が隠れていることがほとんどです。
この記事では、兄弟げんかの背景や心理を理解しながら、親としてどう関わるべきかを具体的にご紹介します。
また、日常の中で取り入れやすい声かけや家庭内の工夫を7つに分けて解説しています。
子どもたちの関係を少しでも良好に保ち、家庭に笑顔を増やすヒントになれば幸いです。
- 兄弟げんかが起きる主な理由
- 上の子がいじわるする心理的背景
- 親がやってはいけないNG対応
- 喧嘩を減らす親の関わり方7選
- 仲直りを促す声かけの工夫
- 比較しない育児の大切さ
- 家庭全体を温かくする実践的アドバイス
兄弟げんかが起きるのはなぜ?その背景を知ろう

まずは、なぜ子ども同士が喧嘩やいじわるをするのか、その根本的な理由を知ることが大切です。
理由を把握すれば、感情的にならずに対応できます。
子どもにとって喧嘩は学びの場
実は、兄弟げんかは成長の一環でもあります。
たとえば、「自分の思いを伝える」「相手の気持ちを知る」といった社会性を学ぶ機会なのです。
一方で、言葉で気持ちを表す力がまだ未熟なため、叩いたり大声を出したりしてしまうこともあります。
そのため、ただ止めるだけでなく、成長の一歩として見守る姿勢も必要です。
親の愛情をめぐる無意識の競争
また、兄弟がいることで「親の注目を奪われた」と感じることがあります。
特に、下の子が生まれた直後は、上の子が敏感に反応する時期です。
そこで、いじわるをしてしまうのは「自分にも注目してほしい」という表現かもしれません。
上の子のいじわるはなぜ起きる?心理的な理由を考える

喧嘩のなかでも、上の子が下の子に意地悪するケースは多く見られます。
しかし、その行動の裏には、上の子なりの葛藤や不安が隠れているのです。
愛されていないと感じてしまう瞬間
たとえば、親が赤ちゃんの世話に集中しているとき、上の子は「自分はもう大切にされていないのでは?」と感じることがあります。
その結果、わざと下の子を泣かせることで、親の注意を引こうとします。
実際には、「自分の存在を認めてほしい」という思いの現れなのです。
新しい役割に戸惑っていることもある
さらに、「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」としての役割を急に求められることへの戸惑いもあります。
たとえば、まだ幼い上の子に「面倒を見てね」と伝えてしまうと、責任の重さに押しつぶされることがあります。
そのため、本人に無理をさせない声かけが重要です。
親がついやってしまうNG対応とは?逆効果を避けよう

兄弟喧嘩が始まると、親も焦って対応してしまいがちです。
しかし、その対応が逆効果になってしまうことも少なくありません。
一方だけを叱るのは逆効果
たとえば、「お兄ちゃんが悪い」「また叩いたの?」というように、一方だけを責めるのは避けましょう。
このような言葉が続くと、上の子は「自分はいつも悪者だ」と感じてしまいます。
結果的に、いじわるがエスカレートしてしまう可能性もあります。
無理に仲直りさせようとするのはNG
また、喧嘩の直後に「すぐ謝りなさい」「仲良くしなさい」と促すのもおすすめできません。
なぜなら、子どもには気持ちの整理が必要だからです。
まずは冷静になる時間を確保し、その後に話を聞くことが大切です。
外部リンク:厚生労働省「子どもの発達と心のケア」
兄弟げんかを減らす!親ができる7つの対策と声かけ術
では、実際に親ができる対応とはどのようなものでしょうか。
以下では、効果的な7つの工夫を具体的にご紹介します。
1. 上の子と1対1の時間をつくる
まず、上の子に「あなたも大切だよ」と伝える時間を意識的に作りましょう。
たとえば、寝る前に絵本を読むだけでも十分です。
こうした積み重ねが、安心感を与えます。
2. 小さな役割を任せる
次に、「お手伝い係」「おやつ配り係」など、簡単な役割を任せてみてください。
役に立っているという実感が、自己肯定感につながります。
3. 気持ちに寄り添う言葉をかける
喧嘩中でも、「そうだったんだね」「嫌だったよね」と共感の言葉をかけましょう。
一方で、「ダメ!」と否定するだけでは、感情を閉じ込めてしまいます。
4. 遊びのルールを一緒に決める
また、トラブルを予防するためには、ルールを一緒に作っておくことが大切です。
たとえば、「順番で遊ぶ」「5分交代する」といった約束を事前に決めるだけで、喧嘩は減ります。
5. 仲良くできたときは必ず褒める
さらに、子どもたちが譲り合えたときや、笑顔で遊んでいるときは積極的に褒めてください。
ポジティブな行動が強化されていきます。
6. 自然な仲直りのきっかけをつくる
「ありがとう」「さすがお兄ちゃん」といった言葉を使うことで、子どもたちが素直に歩み寄りやすくなります。
ただし、無理やり謝らせる必要はありません。
7. 振り返る時間をもつ
喧嘩のあと、「どうすればよかったと思う?」と問いかけてみましょう。
このように、自分で考えさせることで、次の行動が変わってきます。
家庭の空気が変わる!兄弟の関係を育むポイント

兄弟の関係を良くするには、家庭全体の雰囲気づくりも大切です。
以下のポイントを参考に、安心できる環境を整えましょう。
比較しない育児を意識する
「〇〇はできたのに、あなたは?」という言葉は、兄弟関係を悪化させます。
それぞれの成長や個性を認めてあげる姿勢が重要です。
一人ひとりに特別な時間を設ける
忙しい中でも、上の子や下の子それぞれと個別の時間を持つことで、
「大切にされている」という実感が深まります。
関連リンク:【親必見】子供が優しく育つ子育て法|実践的な家庭でできるコツ – 年子パパの子育てハンドブック
兄弟げんかといじわるの対処法まとめ表
| 状況 | 対処法・工夫 |
|---|---|
| 上の子のいじわるが増えた | 特別な時間を設けて愛情を伝える |
| おもちゃの取り合いが絶えない | 遊びのルールを事前に一緒に決める |
| 親がつい感情的に叱ってしまう | 一度気持ちを落ち着けてから対応する |
| 喧嘩のあとギクシャクしてしまう | 振り返りの時間を設けて自分で考えさせる |
まとめ:兄弟喧嘩もいじわるも、親の関わり方で変えられる
兄弟げんかやいじわるは、どの家庭でも起こりうる日常の一部です。
しかし、それをどのように受け止め、どう対応するかで、関係性は大きく変わります。
まずは、子どもたちの気持ちに寄り添うこと。
そして、日々の中で「愛されている」と感じられる時間をつくること。
それが、兄弟の絆を強くし、家庭の安心感を育てていく鍵になるでしょう。