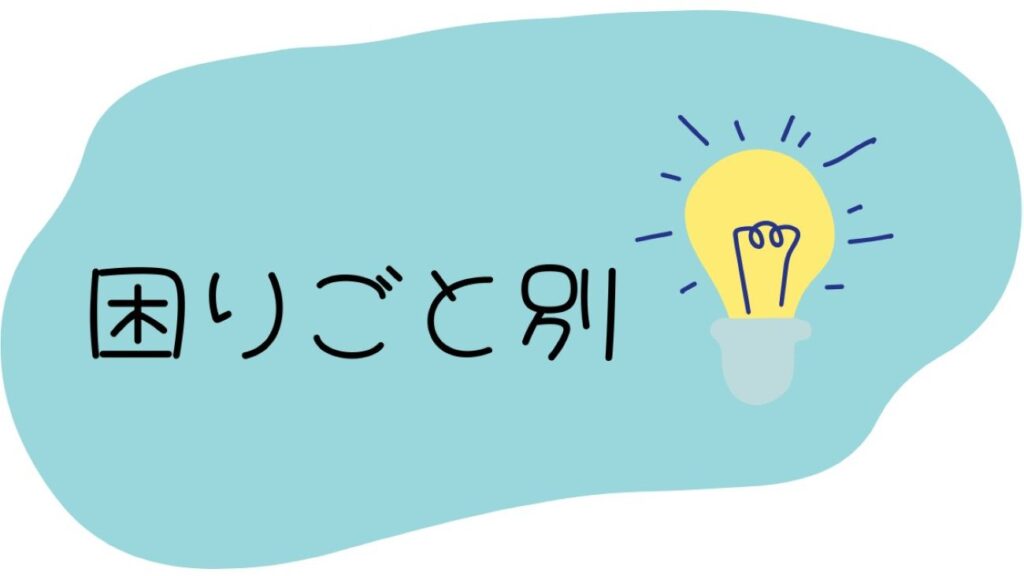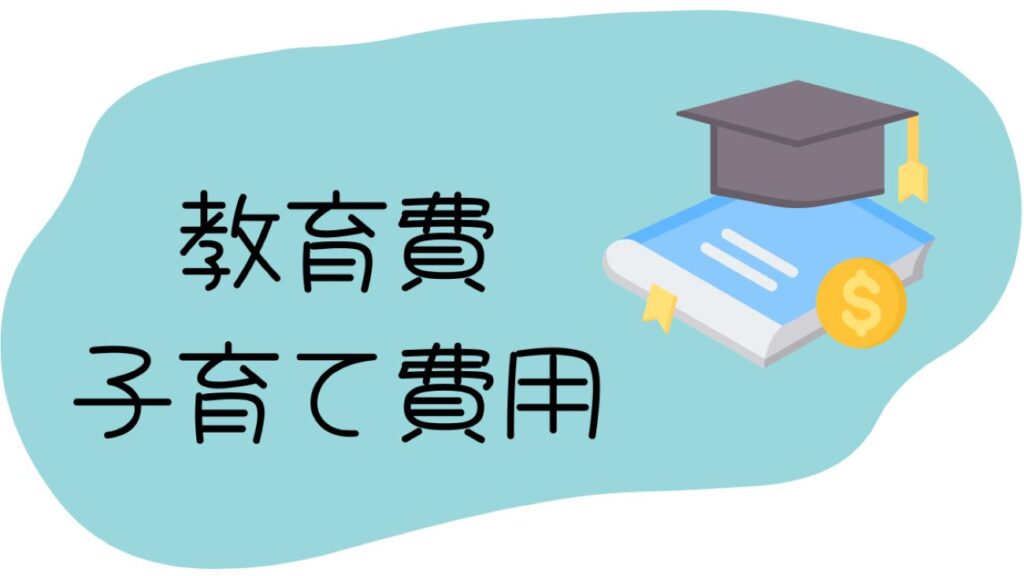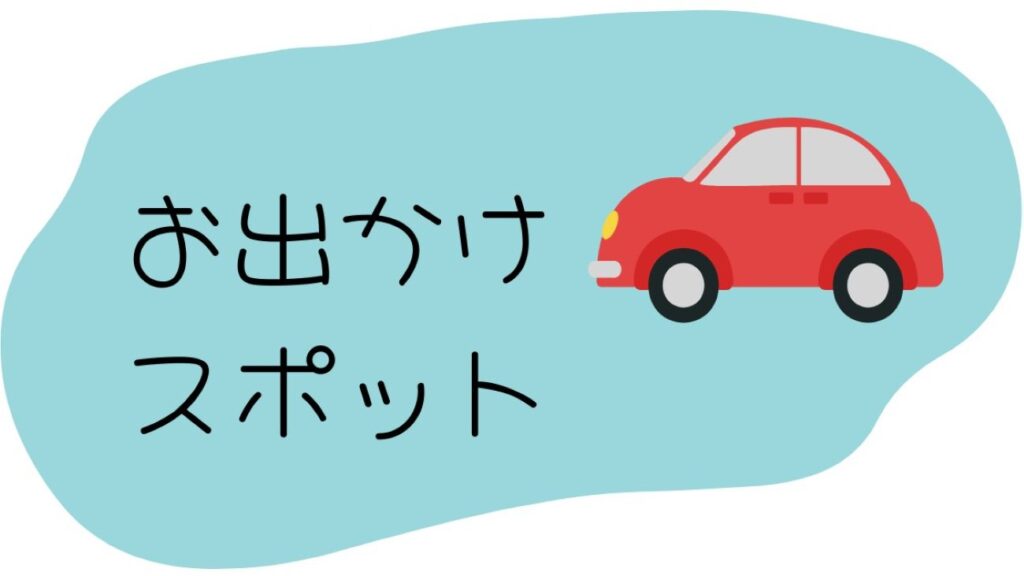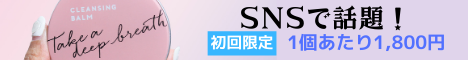【保存版】子どもの言葉の発達時期とは?年齢別の特徴と家庭での関わり方

子どもの「言葉の発達」は、育児において特に多くの親が気にするテーマです。しかし、話し始める「時期」や「スピード」には大きな個人差があり、「うちの子は遅いのでは?」と不安になる方も少なくありません。実際、発達の早い子と比べて心配になってしまう場面は多いものです。
そこで、この記事では言葉の発達の流れとその時期ごとの特徴、家庭でできるサポート法を詳しく解説していきます。また、発達が遅れているかもしれないと感じた時のチェックリストや、相談先についても紹介。この記事を読むことで、不安を減らしながら、親としてできる関わり方が見つかるはずです。
- 子どもの言葉の発達時期とその背景
- 年齢別に見る発達の特徴と注意点
- 発達を促す家庭での取り組み例
- 気になるときの相談のタイミングと機関
- 実践できるチェックリストと親の心得
言葉の発達がもたらすものとは?

言葉の発達は、ただ話せるようになることが目的ではありません。なぜなら、言葉には心の中を伝える役割があるからです。
まず、言葉が使えるようになると、子どもは気持ちや欲求を表現できるようになります。たとえば、「イヤだ」「もっとほしい」といった簡単な言葉でも、自分の思いを伝えられることは安心感につながります。
また、言葉を通して他人と関わるようになれば、社会性も育っていきます。友だちとのやりとりや、大人との会話も、言葉があるからこそスムーズになります。
さらに、言葉は考える力=思考力を育てる土台にもなります。理由を考えたり、順序を理解したりする時、私たちは自然と言葉を使って物事を整理しています。
言葉の発達が育てる3つの力
- 考える力(思考力)
- 気持ちを伝える力(自己表現)
- 人と関わる力(社会性)
年齢別で見る言葉の発達時期
以下は一般的な言葉の発達の目安です。もちろん、個人差があるため、あくまで目安として活用してください。
| 年齢 | 言葉の特徴 |
| 生後0〜6ヶ月 | 声や音に反応、泣き方にバリエーションが出る |
| 生後6〜12ヶ月 | 「アー」「マンマ」などの喃語。声で周囲と関わろうとする |
| 1歳〜1歳半 | 単語を1〜5個程度話す。身振りとセットで表現する |
| 1歳半〜2歳 | 「ママいない」など2語文が始まる。簡単な質問も増える |
| 2歳〜3歳 | 語彙が爆発的に増加。日常的な会話のやりとりが成立してくる |
| 3歳〜4歳 | 「昨日こうだった」と時制を含む表現や感情語も使えるようになる |
脳の発達と「ことば」の関係性
実は、言葉の発達には脳の発達が密接に関係しています。特に、左脳のブローカ野やウェルニッケ野と呼ばれる言語中枢が活性化する時期に、周囲の言葉が刺激となり、言語回路が強化されていきます。
- 0〜3歳は「言葉の感受期」
- この時期に豊かな言語環境にいることで、大きく伸びる
そのため、「話しかけ」「絵本」「歌」など、日々の関わりが非常に大切になります。
言葉を育てる家庭での具体的関わり

1. たくさん話しかける
まずは、どんなときも話しかけることが基本です。ただし、問いかけよりも実況中継型の声かけが効果的。
例:「おくつ履こうね」「おにぎり食べようか」
子どもが言葉を拾いやすいよう、短くて繰り返しのある表現を使うのがポイントです。
2. 絵本や童謡を毎日取り入れる
繰り返しが多い絵本やリズムのある歌は、記憶に残りやすく、言葉の習得をサポートします。
おすすめ絵本
- 『きんぎょがにげた』(五味太郎)
- 『じゃあじゃあびりびり』(まついのりこ)
3. 子どもの言葉を受け止める
子どもが話そうとした言葉が未完成でも、「○○って言いたかったのかな?」と返すことで、会話のキャッチボールが成立します。
発達の遅れ?気になるときのチェックリスト

以下のチェックポイントを参考にしてください。
- 2歳を過ぎても単語がほとんど出ない
- 自分の名前を呼ばれても反応がない
- 同年齢の子と比べて明らかに言葉が少ない
- ジェスチャーすら使わず意思表示ができない
これらに複数該当する場合は、自治体や医療機関へ相談することをおすすめします。
いつ、どこに相談すればいいの?
頼れる相談先一覧
- 地域の保健センター(1歳半・3歳児健診でのチェックも可能)
- 発達外来のある小児科
- 言語聴覚士(ST)による専門評価
詳細はこちら:厚生労働省 発達支援情報
保護者ができる「待つ力」と「育てる力」

子どもの発達において大切なのは、「急がず、焦らず」の姿勢です。というのも、子どもは一人ひとり発達のスピードが違うため、早さだけを基準にするのは適切とは言えません。
たとえば、言葉が遅れているように見えても、それが必ずしも問題とは限りません。環境や関わり方によって、子どもは自然に話す力を育てていきます。ですので、焦って話させようとするのではなく、「話したい」と思える空間を整えることが大切です。
「待つ力」を育てるコツ
子どものペースを尊重するには、次のようなポイントが役立ちます。
- 比べない
他の子と成長を比べず、わが子のペースを信じましょう。 - 話すのを待つ
子どもが自分から話すまで、静かに待ってあげることが大切です。 - 反応してあげる
うなずいたり返事をしたりすることで、伝わる喜びを実感できます。 - 無理に話させない
「話しなさい」と言うのではなく、気持ちをくみ取りながら寄り添いましょう。
「育てる力」は環境づくりから
また、日々の生活の中でできる工夫もたくさんあります。
- たくさん話しかける
日常の中で自然な会話を増やしましょう。 - 絵本や遊びで言葉を育てる
楽しく学べる環境が、好奇心を引き出します。 - 気持ちを言葉にする
「楽しいね」「悔しかったね」など感情を言語化してあげましょう。 - 安心できる空間をつくる
失敗しても大丈夫と思える安心感が、言葉の芽を育てます。
焦らず、比べず、寄り添う。この3つを意識するだけで、子どもは自分のペースで大きく育っていきます。保護者にできることは、「信じて待つ」こと。そして、「安心できる毎日」を一緒に過ごすことなのです。
まとめ|ことばの発達を見守るために
言葉の発達には個人差があります。だからこそ「比較」ではなく「観察」が必要です。大切なのは、子どもの今を見つめ、少し先を一緒に育てていく姿勢です。焦らず、でも見逃さず。そして、迷ったときは相談することも、立派な愛情のひとつです。