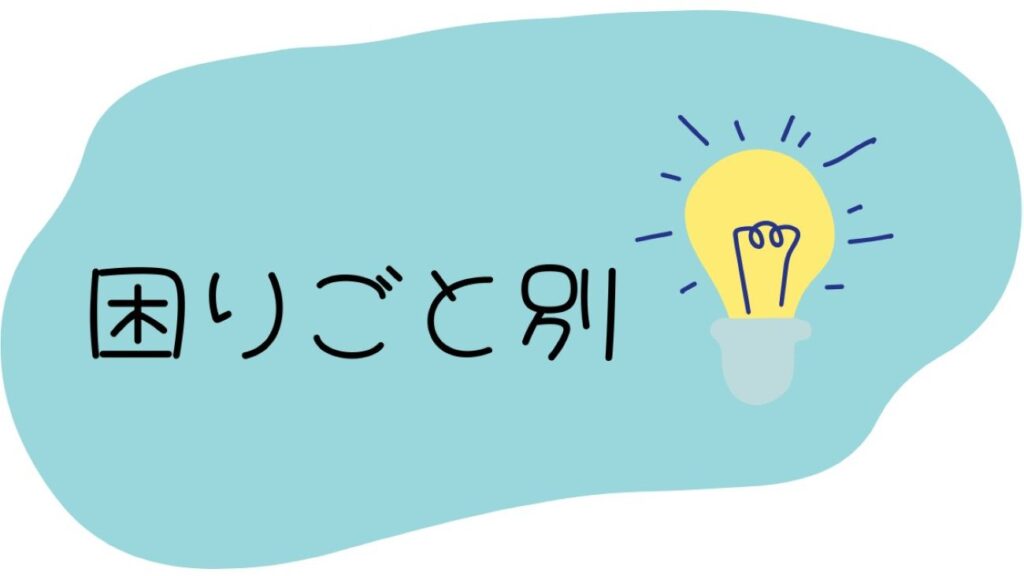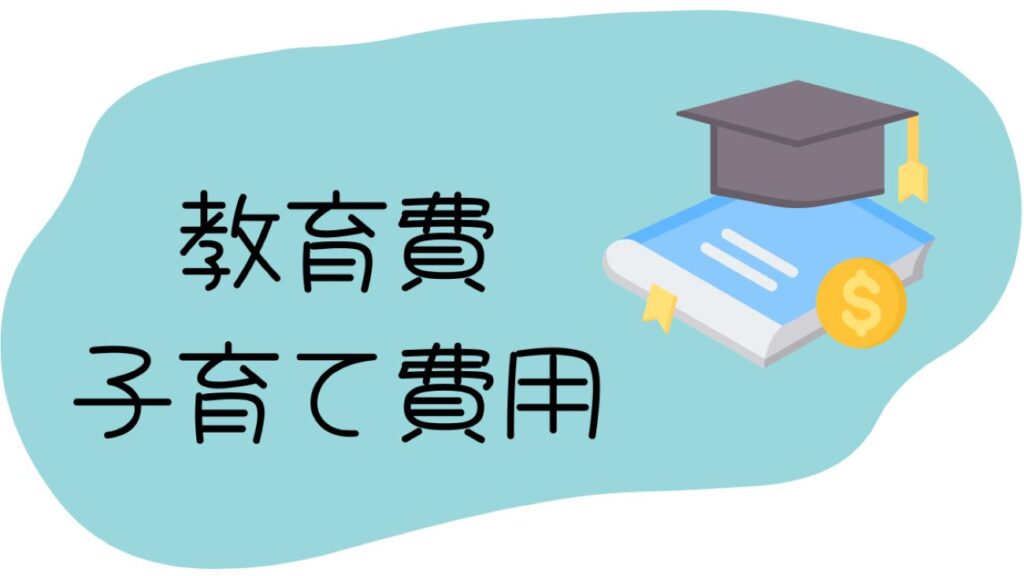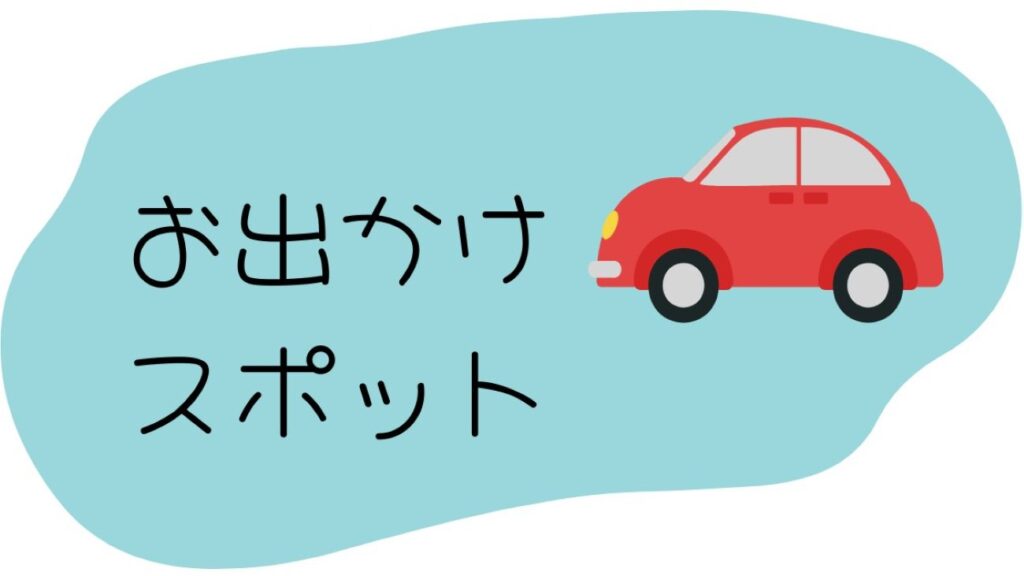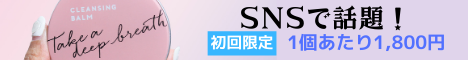子育ての中で、「どうしてうちの子は言うことを聞かないの?」と悩む場面は多いですよね。一生懸命伝えているのに、聞こえていないふりをしたり、わざと逆のことをしたり…。
しかし、実はその“聞かない”行動には、子どもなりの理由やメッセージが隠されているのです。
この記事では、子供が言うことを聞かない原因を心理や発達の観点から解説します。
さらに、今日から使える声かけのコツや、年齢に合った対処法もご紹介します。
親子の関係が少しずつ変わっていくような、実践的なヒントをまとめました。
- 子供が言うことを聞かない心理的な理由
- 親がやってしまいがちなNG対応
- 年齢別の対応ポイント
- 効果的な声かけ・ルールづくりのコツ
- 子供との信頼関係の築き方
子供が言うことを聞かないのはなぜ?

まず最初に理解しておきたいのは、
子供が「言うことを聞かない=悪いこと」とは限らないということです。
言うことを聞かないのは成長の証拠でもある
たとえば、2歳〜5歳ごろに見られる「イヤイヤ期」は、
自分で考えたい、決めたいという自我の芽生えによるものです。
そのため、「嫌!」「やだ!」といった反応は自然なプロセスなのです。
それに加えて、まだ感情を言葉でうまく伝えられないため、
行動で表現するしかないという背景もあります。
ですから、「聞かない」というよりも「うまく伝えられない」のです。
言うことを聞かない時に親がついやってしまうNG対応

子供が言うことを聞かないと、どうしてもイライラしてしまいますよね。
しかし、反応の仕方によっては、かえって逆効果になることもあります。
1. 子供に感情的に怒鳴る
たしかに、その場では子供が静かになることがあります。
しかし、繰り返すうちに**「怒られるから従う」**という態度になり、
自分で考えたり、納得したりする力が育ちにくくなります。
2. 言うことを聞かないと長々と説教する
大人にとっては筋道立てた説明でも、
子供には長すぎる言葉は理解できません。
途中で聞くのをやめてしまったり、内容を覚えていないことも多いです。
3. 命令ばかりになる
「早くしなさい」「それはダメ!」といった命令形は、
子供にとっては受け身の関係に感じやすいもの。
結果として、「自分で決めたい」という気持ちが強まり、反発しやすくなります。
年齢別に見る!言うことを聞かない子への対応法
とはいえ、子供の年齢によっても反応や理解度は異なります。
そこで次に、年齢ごとの特徴と対応のコツをご紹介します。
| 年齢 | 特徴 | 適した対応方法 |
|---|---|---|
| 2〜3歳 | 自我が強くイヤイヤ期真っ盛り | 短い言葉と肯定的な選択肢 |
| 4〜5歳 | ごっこ遊びやルール理解が進む | 共感を伴う説明と簡単なルール |
| 6〜8歳 | 理解力が高まるが自分中心 | 理由を説明しつつ納得させる |
| 9歳以上 | 思春期の入り口で感情が複雑 | 対話を重視・自主性を尊重 |
たとえば、4歳の子に「なんでまたやったの?」と聞いても、
具体的な理由を説明するのは難しいかもしれません。
ですから、年齢に合った伝え方を意識しましょう。
声かけを工夫すれば子供は言うことを聞く!
次に、日常で試せる「伝え方」の工夫についてお話しします。
実は、ほんの少しの言い方の違いで、子供の反応が大きく変わることがあるのです。
1. 「一緒にしよう」と誘う
たとえば、「片付けなさい」ではなく、
「一緒に片付けようか」と言うだけで、
子供のやる気が変わることがあります。
なぜなら、「命令」ではなく「協力」だからです。
2. 子供に選ばせる
また、「今お風呂に入る?それとも5分後?」といった選択肢を与えると、
子供は自分で決めたという納得感が得られます。
その結果、スムーズに行動に移しやすくなります。
3. ルールは短く、具体的に伝える
長々とした注意よりも、「お店では走らないよ」など、
一文で伝えられる具体的な言葉の方が効果的です。
参考リンク:ベネッセ|自分で考えて行動できる子になるには「段取り力」と「習慣化」が大事
それでも子供が言うことを聞かないときの対処法

どんなに工夫しても、子供が聞かないこともあるでしょう。
そんなときは、別のアプローチも検討してみましょう。
1. 子供に結果を伝え、経験させる
たとえば、「靴を履かないとお出かけできないよ」と伝えたうえで、
実際に行かない選択をすることも、ひとつの学びです。
これは、「結果と行動の因果関係」を実感させる方法です。
2. 第三者の力を借りる
保育園の先生や祖父母など、信頼できる第三者の言葉は、
意外と素直に聞けることがあります。
ですので、無理に自分だけで抱え込まないことも大切です。
関連リンク:2歳児の癇癪が収まらない…親子で笑顔になれる7つの対策法 – 年子パパの子育てハンドブック
親子関係を育てるための習慣づくり

最終的に、子供が言うことを「聞こうと思える」関係性こそが大切です。
つまり、「親の言葉を受け入れやすい状態を日頃から育てる」ことです。
1. 子供との小さな約束を守る
「寝る前に絵本を読もうね」といった約束を、
きちんと守ることで信頼関係が育まれます。
子供は親の行動をよく見ています。
2. 肯定的な声かけを意識する
「できたね」「ありがとう」などの言葉は、
子供の心を満たし、安心感につながります。
これにより、反発ではなく信頼で行動する力が育つのです。
まとめ:聞かない子には、伝わる関係づくりが鍵
子供が言うことを聞かないのは、「困らせよう」としているわけではありません。
多くの場合、それは「気持ちをうまく表現できないサイン」なのです。
ですから、まずは子供の気持ちに寄り添う姿勢を持ちましょう。
また、年齢や性格によって対応も変わってきます。
大切なのは、親も完璧を目指さず、少しずつ関係を育てていくこと。
日々の中で、小さな信頼の積み重ねが大きな変化につながります。